
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
暦年贈与・毎年同じ額は危険?
相続対策として110万円の暦年贈与
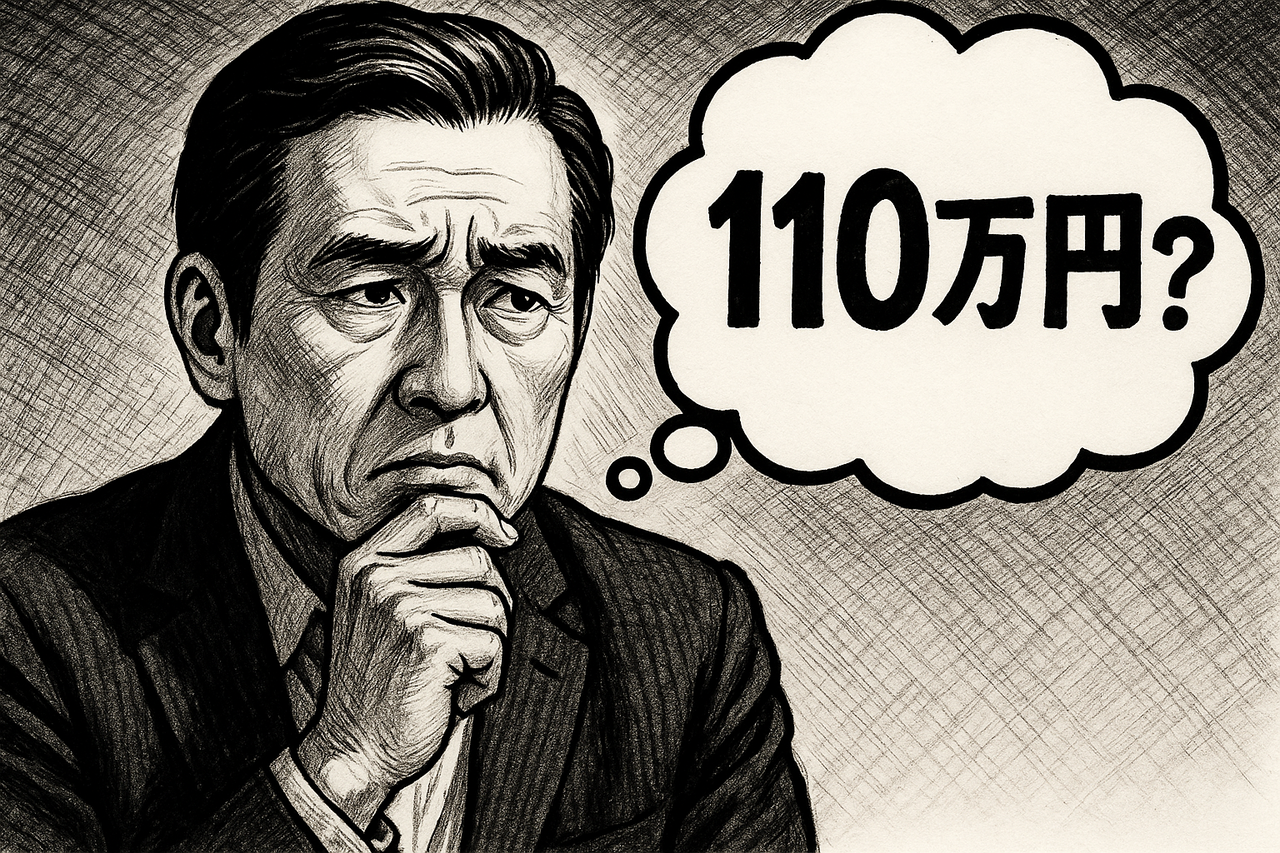
相続対策として多くの家庭で利用されているのが「暦年贈与」です。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に基づいて贈与税を計算する制度を指します。
贈与税には基礎控除があり、年間110万円までは贈与税がかからないため、毎年110万円以内で贈与を受ければ贈与税の負担なく財産を移転することが可能です。
この制度を利用して、財産を少しずつ減らし、将来の相続税の課税対象額を減らす仕組みです。
例えば、子どもが2人いる家庭であれば、毎年110万円ずつ2人に贈与することで、年間220万円を無税で移すことができます。10年間続ければ2,200万円、20年間なら4,400万円もの財産を贈与税なしで渡せる計算になります。
ただし、暦年贈与は便利である一方で、誤った理解や実務上の注意点を見落とすと「危険」と言われることがあります。その代表例が「毎年同じ額を渡すと危ない」という俗説です。
毎年同じ額は危ないはウソ?
相続対策の本などでも「毎年同じ金額を贈与していると危険」と書かれているものもあります。相続に詳しい税理士さんに伺ったところ、これは、税務署が「一括贈与の分割払い(定期贈与契約)」とみなして課税するのではないかという不安から広まったものだそうです。
しかし、実際には、単に毎年同じ額を贈与しているだけで定期贈与契約と判断されることはありません。定期贈与契約とは、最初から「1,100万円を10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与する」といった包括的な契約を結んでいる場合に問題となるものです。
一方で、毎年「贈与するかどうか」をその都度決めて、贈与契約書を作成し、銀行振込の記録を残すといった実務をきちんと行っていれば、定期贈与契約と判断されることはないと考えられます。つまり「毎年同額の贈与をしている=危険」というのは誤解に過ぎません。
定期贈与契約と区別するために
暦年贈与を行う場合に大切なのは、定期贈与契約と区別することです。前述の通り、定期贈与契約とみなされると課税対象額が一気に増えます。したがって、毎年の贈与がそれぞれ別個の契約であることを明確にしておく必要があります。
実務的には次のような証拠(エビデンス)が有効です。
毎年「贈与契約書」を作成すること。簡単な書式で構いませんが、贈与者と受贈者の自筆の署名、押印があると望ましいです。
送金の際は、銀行振込みで履歴を残すこと。現金手渡しでは証拠が残りにくく、後日の証明に困る場合があります。
このように、一括での約束がなく、その都度の判断で贈与していることが明確であれば、税務署から定期贈与契約と判断される可能性は極めて低くなります。また、名義預金と疑われることを避けるため、受贈者が自分自身で管理している口座宛に送金することも大切です。
相続開始前から7年間に注意
暦年贈与を行う際、近年特に注意が必要なのが「相続開始前7年間の贈与」です。2023年の税制改正により、従来は3年間だった相続財産への加算期間が7年間に延長されました。
これはどういうことかというと、贈与者が亡くなった際に、その亡くなる前7年間に行われた贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になるというルールです。
ただ、相続開始の時期(死亡したとき)に合わせて計画を立てることは実際には不可能です。したがって、暦年贈与を行う場合は、余裕をもって計画を立てることが必要です。
孫に贈与するのもアリ
暦年贈与は子どもだけでなく、孫に対して行うことも可能です。子どもが第一順位の相続人であれば、孫は相続人ではありませんので、相続開始前7年間の贈与の持ち戻しの対象外となります。
さらに、親から子へ、さらに子から孫へと財産が移る場合、通常、2回相続税の対象となりますが、直接孫へ暦年贈与を行えば、子を経由せずに財産を移せるため、長期的に課税対象額を減らせる可能性もあります。
まとめ
近年は、高齢化が進み、財産を受け取る相続人の年齢も高くなる「老老相続」が増加しています。この状況では、なかなか若い世代までお金が行き渡らず、経済のためにもよくありません。
政府としても、この状況を打破するために、教育資金、結婚資金、子育て資金の贈与に非課税枠を設ける等、生前贈与を促すため様々な税制改正を行っています。
暦年贈与は正しい方法で行えば、有効な相続対策となります。
ただし、「贈与し過ぎて、生活費が足りなくなってしまった…」ということがないよう、無理のない計画の下で行ってください。
手続き等で不安なときは、相続専門の税理士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
2025年9月
司法書士 日永田一憲
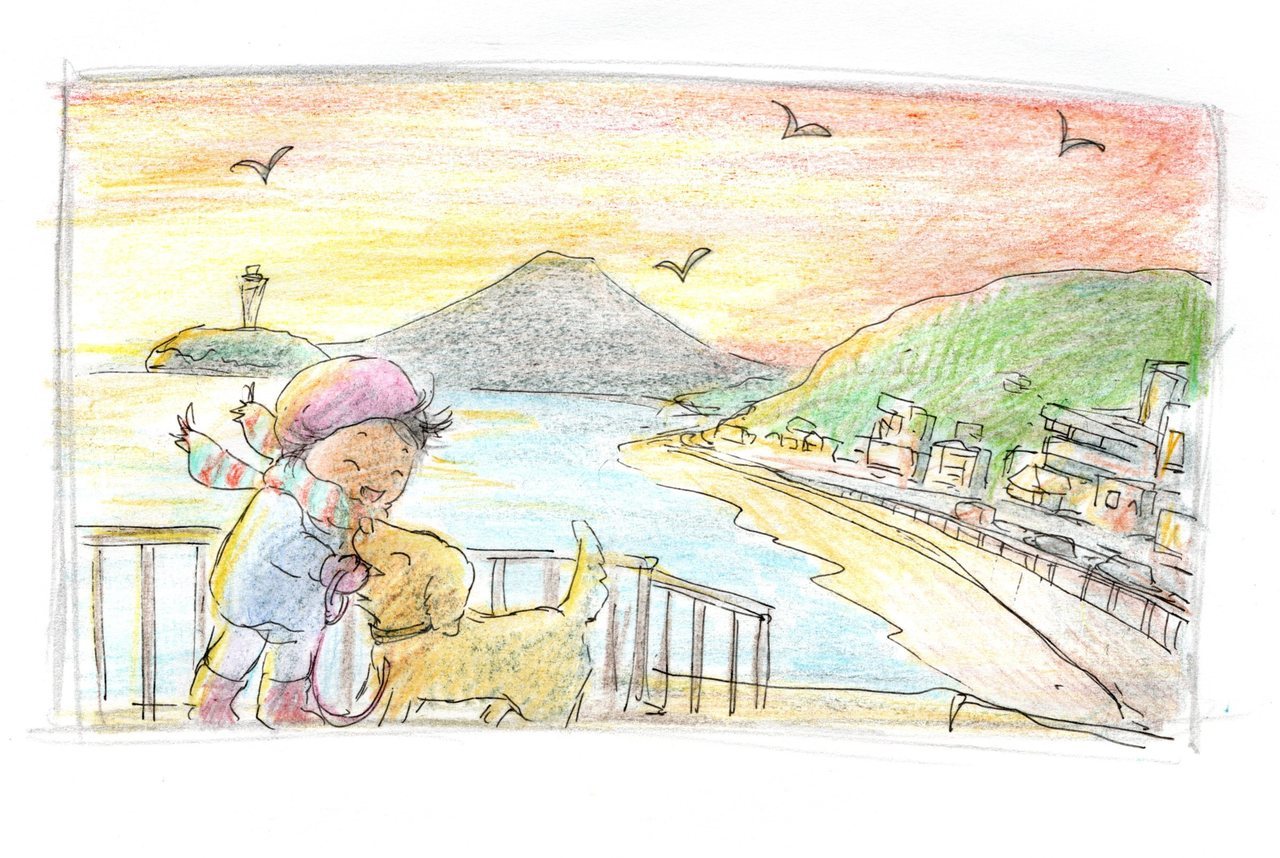
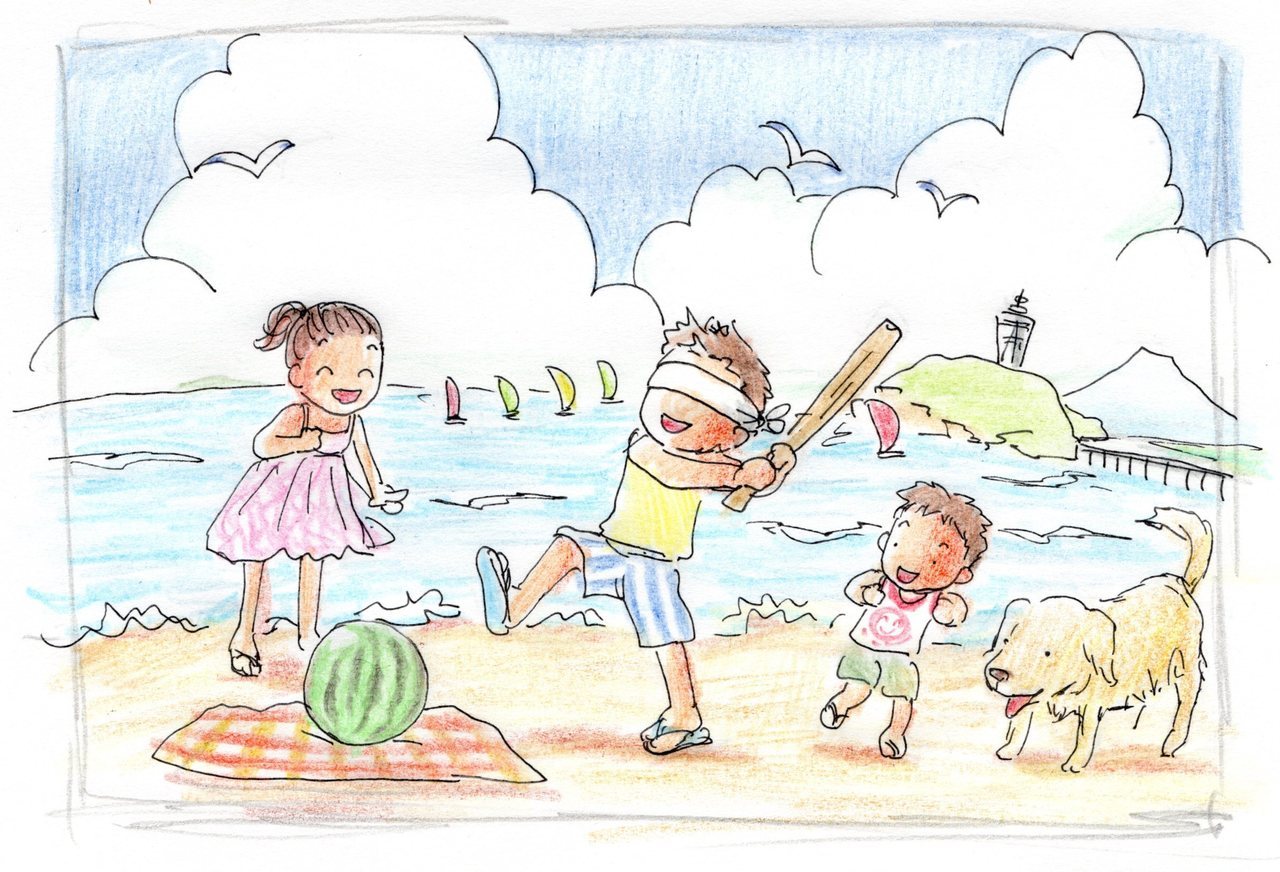
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



