
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
かもめの相続コラム:徳川家康の相続対策
江戸時代をつくった徳川家康の相続対策

■250年の平和な時代は「相続対策」からはじまった
長い戦乱の時代から平和な世へ導いた徳川家康。
家康自身が本当に心から「平和な世の中」を望んでいたかどうか、今となっては知る由もありませんが、
平和な世=徳川家の権力安定
と考えていたことは間違いないと思われます。
まずは、徳川家康の略歴から。
■略歴
- 1542年 1歳 三河国で誕生
- 1547年 6歳 織田家の人質
- 1549年 8歳 今川家の人質
- 1560年 19歳 桶狭間の戦い
- 1562年 21歳 織田信長と同盟
- 1582年 41歳 本能寺の変
- 1586年 45歳 豊臣秀吉と和睦
- 1598年 57歳 豊臣秀吉死去
- 1600年 59歳 関ケ原の戦い
- 1603年 60歳 征夷大将軍
- 1615年 74歳 大阪冬の陣
- 1616年 75歳 死去
家康が生まれた三河の国(愛知県東部)は、地理的に今川家と織田家に挟まれ、物心ついてから二十歳ぐらいまでは、ほとんどの時期を人質としての暮らしました。
19歳のとき今川方として桶狭間の戦いに参戦しますが、今川家は敗戦の後、急速に力を失っていきます。
落ち目の今川家から離れ織田信長と同盟を結びますが、両者の力の差は歴然。対等ではなく下請け的な地位に近い関係だったと思われます。同盟後、約20年間信長のもとで励みます。
41歳のとき本能寺の変が起こり信長がこの世を去ります。実質的にはこのときが「真の独立」といえるかもしれません。
その後、勢いに乗り天下統一目前の豊臣秀吉と対立しますが、45歳のとき秀吉と和睦。
秀吉の死後、関ケ原の戦いで実質的に天下をとったのは59歳。
この時点から亡くなる75歳までの15年間で様々な「相続対策」を行っていきます。
現代の75歳と違い、平均寿命が40歳そこそこの当時としては相当な長寿。
また、注目すべきはその「健康寿命の長さ」です。亡くなる前年まで合戦の指揮を執っており、当時の資料からも心身とも健康だったと考えられます。
相続対策は、心身ともに健康なうちから始めるべきという良いお手本です。
■相続対策① 莫大な富の蓄積=圧倒的な軍事力
◆日本史上最大の資産家で倹約家
徳川家康は、日本史上最大の資産家だったといわれてます。時代が異なるので単純な比較はできませんが、藤原道長より、平清盛よりも、お金持ちだったといれています。
主な資産の内容は、自身の直轄領400万石、徳川家全体では800万石(日本全体の25%にあたります)。
石高は食料生産の量だけではなく、兵力動員数を意味することから、圧倒的な軍事力を有していたことが明らかです。
例えば、同じ時代の英雄と比べても、織田信長(家臣も含め)は最大400万石、豊臣秀吉の直轄領200万石です。徳川家康がどれだけの領地持ちだったか分かります。
また、土地の他に、日本各地の金山銀山の経営、貨幣鋳造の権利も独占的に手にしていました。これだけの資産家でありながら、普段は、服装も質素にするなど相当な倹約家でした。
では、どのように莫大な資産を築いたかみていきましょう。
徳川家康が大きく資産を増やしたのは生涯で4回ありました。
<桶狭間の戦い>
今川方として参戦するが、敗戦後、今川家から離反し三河を平定。
<本能寺の変>
同盟相手の織田信長が討たれた後、織田家の支配地(旧武田領)甲斐、信濃へ侵攻。
<小田原征伐>
豊臣秀吉に従い、同盟相手であった北条氏討伐に参戦。旧北条領の関東250万石を得る。
<関ケ原の戦い>
豊臣家の内部分裂から始まった戦いに東軍の旗頭として参戦。敗れた西軍から600万石を没収し、300万石以上を徳川家へ加増。また、豊臣家の支配下にあった主要な金山、銀山、貿易港を獲得。
<効率の良い稼ぎ方>
これらの事例から効率よく財を築いていたことが分かります。業務効率化の観点からするとすばらしく優秀です。
悪く言えば「火事場泥棒的」な稼ぎ方にもみえますが、数少ないチャンスを確実にモノにしてきた時勢眼と行動力は並じゃありません。
■相続対策② 仮想敵の弱体化
◆朝廷、寺社の弱体化
歴史上の権力者達の悩みの種、トラブルの元になりやすい朝廷や寺社を法により行動を制限し、力を削ぎました。
代表的な禁中並公家諸法度、寺院法度とも家康の法律顧問的なブレーン、金地院崇伝(臨済宗)の起草とされています。
◆大大名、有力大名の弱体化
関ケ原の戦いの後、豊臣家222万石→65万石、毛利家112万石→30万石、上杉家120万石→30万石と大幅に石高を減らし、徳川家に対抗できる大名を弱体化させました。
関ケ原の戦いで味方についた福島家、細川家など有力大名は加増しつつも遠国へ転封し、中央の権力から遠ざけました。
◆家臣の弱体化
徳川家の仮想敵は外様の大名に限りません。
家臣や譜代の同盟者が力を持ちすぎないよう、大きな領地は与えず、官僚的な地位、仕事を与え政権運営を任せる施策をとり、財力と権力が結びつかないようにしています。
譜代大名の最大は井伊家30万石。他は15万石以下です。
家臣の力が強すぎて、相対的に弱体化した足利将軍家の失敗例から学んでいたのかもしれません。
■相続対策③ 相続制度の整備
◆長幼の序の確立
相続順位、嫡子絶対の原則(長幼の序)を確立させました。
庶子忠長を三代将軍候補に推す動きを封じ、嫡子家光を後継者に指定した話は有名ですが、これがが徳川時代を通じて絶対的な先例となり、たとえ親でも跡継ぎを変えることができないルールが日本中の大名家、武家に浸透しました。
結果的に、前時代(室町、戦国)と比べ、大名の相続争いを大幅に減らすことができました。
◆徳川家の世襲
家康は、征夷大将軍に任官後、わずか2年で秀忠にその職を譲りました。このことは、徳川家が代々「武家の棟梁」の地位を継ぐことを世間にアピールすることが目的であったと思われます。
◆相続人不存在への対策
徳川本家に跡継ぎが絶えた場合でも跡継ぎ候補を絶やさない策で、分家の尾張家か紀州家から養子を出すことになっていました。実際に8代将軍吉宗は紀州家の出身です。
また、尾張藩、紀州藩それぞれにも分家があり、跡継ぎ不存在対策が徹底されていました。
■相続対策④ 教育、思想のコントロール
◆儒学の奨励
林羅山を抜擢し、朱子学を幕府の公式な学問(官学)と定めました。
朱子学とは、身分、秩序、礼節を重んじる学問で、人間の身分の上下は、天地に上下があるように定められているという上下定分の理を説き、己を慎み相手を敬う「敬」を重視し、身分秩序をわきまえた生き方を推奨しました。
このことは、社会の革命やイノベーションを防止し、政権運営を安定化することに大きな効果があったと考えられます。
■まとめ(参考にできること)
江戸時代を通じ、家康が行った「相続対策」が後年まで大きな影響力を持ち続けていたことがお分かりいただけたことと思います。
また、時間をかけて財産を築くことや相続トラブルの防止など現代でも参考にできることがたくさんあります。一度、自分にあてはめ、よく考えてみたいものです。
2022年7月
司法書士 日永田一憲
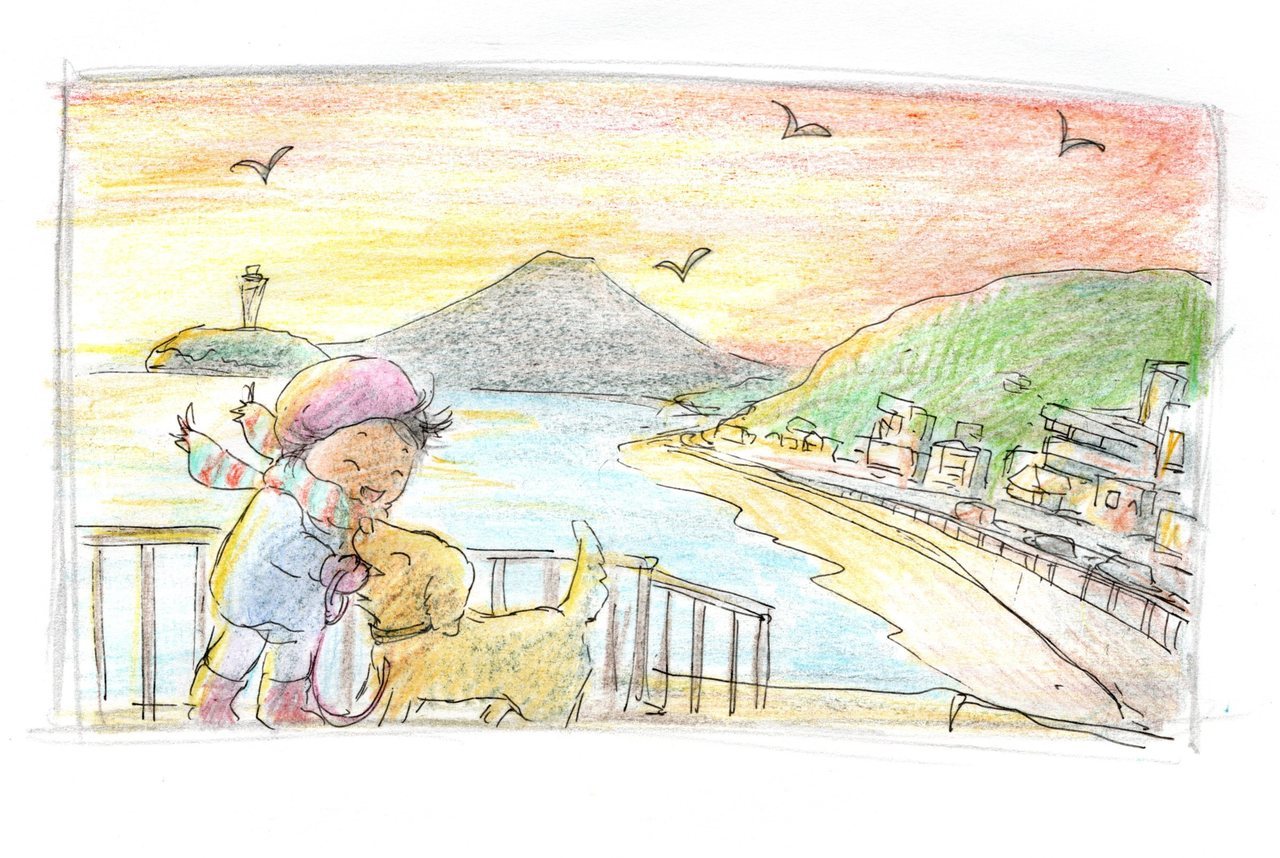
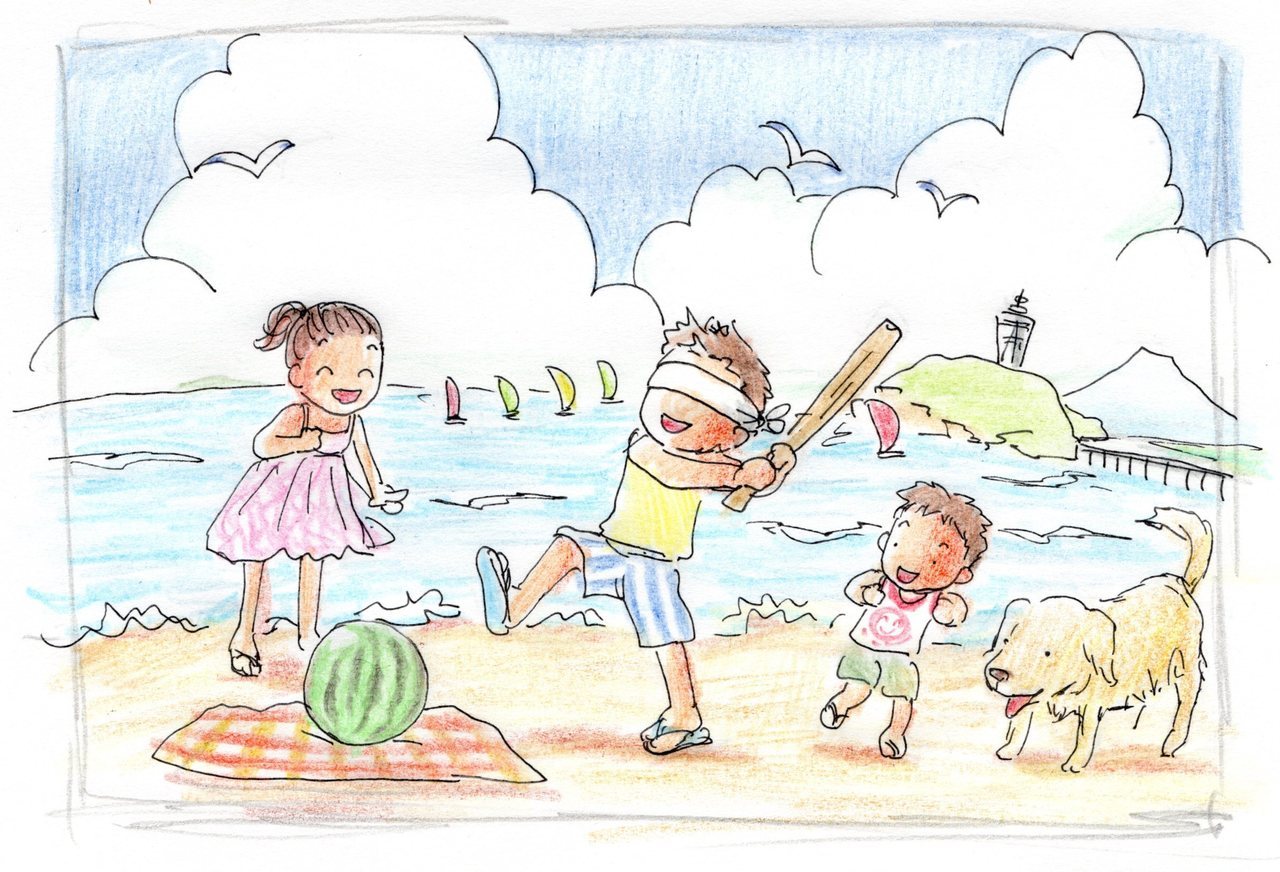
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



