
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
かもめの相続コラム:デジタル遺産の相続
デジタル遺産の相続(暗号資産、SNS等)

相続実務では、まだほとんど経験する機会はありませんが、昨今、デジタル遺産という言葉を耳にすることが多くなっています。
デジタル遺産とは、具体的に何を指すのかにについて、現時点では、法律上の明確な定義はありません。
相続時に問題となるのは、大きく分けると、次の3つがあげられます(複合的、横断的にに関わり合っているので分けるのは難しいが)。
- インターネット銀行、証券、暗号資産(仮想通貨)
- パソコン、スマートフォンなどのデジタル機器及びデータ
- ウエブサイト、SNSなどのオンライン上のデータ
■インターネット銀行、証券会社
インターネットを利用した金融サービスは、急速に利用者が増えており、大手金融機関においても、紙の通帳はいつ廃止されてもおかしくないような勢いです。
近い将来、この方法がスタンダードになってくることでしょう。
相続手続きに限って考えると、被相続人の取引先が分かれば、従前の金融機関のとおり、相続手続きをすすめることができます。
ただ、インターネット専門の金融サービスの場合、郵送による案内が送られてくることは稀ですので、被相続人がどの銀行や証券会社を利用していたかが、相続人は分からないというケースが起こりえます。
あらかじめ、利用している銀行や証券会社を推定相続人に伝えておくか遺言書やエンディングノートに取引のある金融機関名だけでも記載しておけば、このような事態は防げると思います。
被相続人が利用していたサービスが分からない場合は、パソコン、スマートフォンなどのデジタル機器のソフトウェア、アプリケーション、ブラウザのブックマーク、メール履歴など調査してみるのがよいでしょう(ロック解除の問題は後述)。
■暗号資産(仮想通貨)
また、暗号資産(仮想通貨)についても統一的な見解はありませんが、相続の対象となることに異論はないと思います。
国税庁の「仮想通貨に関する税務上の取り扱いについて(FAQ)」においても、暗号資産に相続税が課税されることが明示されています。
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/faq/pdf/04.pdf
ビットコイン等の暗号資産を自分自身で管理していた場合、秘密鍵の紛失(不明)により、保有していた暗号資産にアクセスできなくなるという事態が起こりえます。ビットコイン総量のうち、約2割がアクセス不能により、すでに遺失しているという説もあるくらいです。
取引所(仮想通貨交換業者)を通じて仮想通貨を取引していた場合は、取引所に相続の届け出をすることにより(方法は取引所により異なります)、相続手続きをすることができるようです。
■オフラインデータの遺産分割
パソコン、スマートフォンなどのデジタル機器自体は、他の動産と同様、相続の対象となります。
デジタル機器内の文章データ、写真、音楽、イラスト等も「被相続人の財産の一切の権利義務」として、それぞれ相続の対象になると考えられます(クラウド上に保存したものも同様)。
したがって、遺産分割においては、同一機器内に保存されている文章データは○○が、写真は○○が相続するという分割も可能です。
■ロック解除の問題
ほとんどのデジタル機器は、ロック機能が備えられています。
被相続人のプライバシーの問題は残りますが、ロックの解除自体は相続人がすることがでるという考え方が一般的です。但し、ロック解除には、データ消失のリスクが伴いますので、相続人複数の場合は、全員の同意があったほうがよいでしょう。
相続人がスマートフォン等のロック解除のパスワードやピンコードを知らない場合、携帯電話のキャリア(ドコモ、エーユーなど)に頼んでも、ロック解除には応じてもらえません。
ちなみにアップル社では、相続人等から裁判所命令等の法的書類があれば、ロック解除に応じてくれるようです(日本ではどのような書類がこれにあたるのかは分かりません)。
https://support.apple.com/ja-jp/HT208510
また、アップル社では、前もって自分が死亡した場合のアクセスできる人を登録しておく方法も規定されています(故人アカウント管理連絡先)。
https://support.apple.com/ja-jp/HT212361
■SNS等の利用規約
ウエブサイト、SNSアカウントなどのオンライン上データの相続には、利用規約により相続可能とされていれば、相続の対象となります(利用規約自体が有効か争われるケースもあるが)。
一般的に、多くのSNSアカウントは、一身専属的であり、規約で第三者への譲渡(特定承継)や相続(包括承継)を認めていません。
■一身専属性と財産的価値
一身専属的とは、端的にいえば、その人でなければ成立しない又は認められるべきではないような権利や義務のことです。たとえば、委任契約における委任者・受任者の地位、扶養義務請求権などがあげられます。
多くのサービスでは、利用者が亡くなった場合の措置を規約で定めており、フェイスブックでは、亡くなった方の相続人からの申出により、「追悼アカウント」への移行が原則とされています。また、相続人の希望によりアカウント削除することも可能です。
https://ja-jp.facebook.com/help/275013292838654/?helpref=hc_fnav
これらのオンライン上のサービスについては、ユーザー層が若いため、それほど相続の事例は多くありませんが、SNSやブログ等により多額の広告収入を得ていた場合等は、財産的価値と一身専属性の問題が今後争われることになるかもしれません。
■デジタル遺産の相続対策
では、デジタル遺産の相続対策として、何をすればよいのか?
時代に逆行するようですが、現時点では、紙に残すことが一番確実と思われます。
エンディングノートや相続時メモなどをデジタル機器内に残しても、アクセスできなければ、だれもその内容を知ることはできません。
少なくとも、
- 利用しているデジタル系金融機関、決済サービス
- 愛用しているデジタル機器及びデータの利用又は処分方法
- ウェブサイトやSNSアカウントに関する希望(追悼、削除、閉鎖)
については、紙に記して、相続人に伝わるようにしておいたほうがよいでしょう。
また、利用していないデジタル金融サービスやSNSアカウント等は、生前のうちにできるだけ整理しておくと、そのぶん相続人はラクになります。
デジタル遺産の相続、まだ実例はそれほど多くありませんが、10年先には、公共料金等と同様、当たり前の手続きになっているかもしれません。
2022年1月
司法書士 日永田一憲
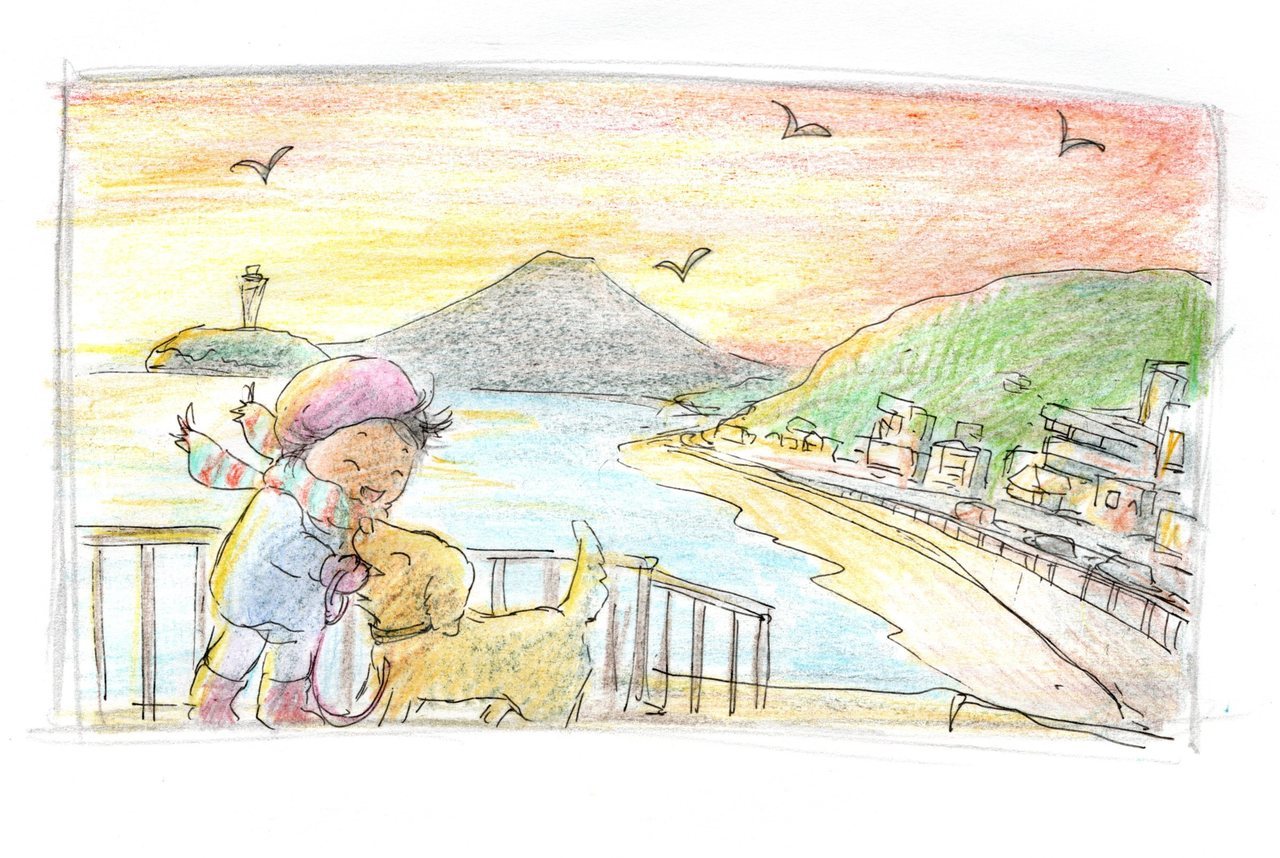
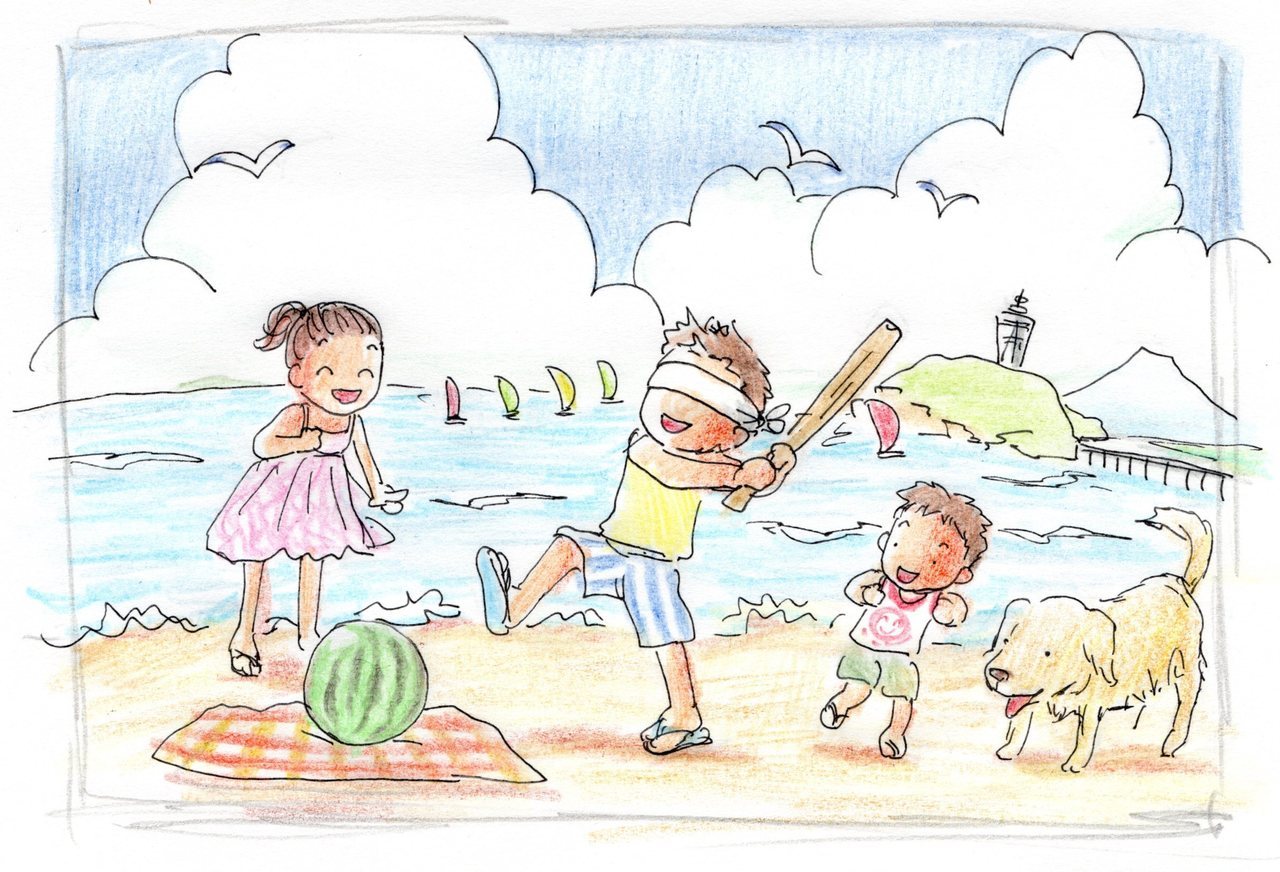
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



