
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
かもめの相続コラム:低成長・少子化時代の相続
低成長・少子化時代の相続、昭和の常識は通用しない

■給料が10倍!戦後50年は特異な時代
私は昭和44年生まれ。
将来のことを考えるとき、誰に言われたわけでもないのに、
「親の金はあてにするな」
「財産は自分で築くもの」
という「常識」がなんとなく頭にあった。
その常識は、ある時期までは、正しかったかもしれない。
戦後復興、人口増加、産業構造の変化等、様々な要因が絡み合って、1956年から1973年までは、平均9.1%の経済成長率を記録している。
急激な成長は、過去から相続した財産をみえにくくし、相続財産(親の金)はその重要性を失っていく。先代の所得があまりにも小さくみえるからだ。
財産を築くためには、労働と勤勉、職業的成功によることが最短ルートであり、道徳的にも立派なこととされた。
しかし、歴史的にみると、戦後の50年、1945〜1995年までが特異な時期であったことは明らかだ。
私が大学生の頃(1990年頃)、オジサン達から、物価の違いの例え話としてよく聞かされた言葉がある。
「当時の初任給は、2万円の時代だよ!」
(1962年の大卒初任給は約2万円)
全然ピンとこなかったが、
「私も50歳くらいのオジサンになったら、初任給200万円の若者に向かってこんな話をするんだろうか・・」
と思っていた。
今から約30年前の1992年、私の初任給は22万円だった。
(1962年の11倍!)
そして現在、2021年の大卒初任給の平均は約22万円。
10倍どころか、同じ金額ではないか。
日本はデフレだからという理由もあるかもしれない。
しかし、世界的にみても、1913年から2012年までの100年間の経済成長率は、平均1.6パーセント。戦後日本の9%には到底及ばない。
ちなみに高度成長期と呼ばれる1974年の預金金利は8%。100万円預金すると、10年後には220万円。
私の親世代はそんな時代を経験している。
歴史上、稀に見る「相続財産」の重要性が低い時代だ。
30年前、初任給の話をしていたオジサン達も、今は80歳前後。
時代は大きく変わったが「親の金はあてにするな」という考え方は、そんなに変わっていないと思われる。
■少子化の影響
また、子供の数が減り、相続人一人当たりが受け継ぐ相続財産は、これからも増えていくことが予想される。
昭和24年(1949年)の平均出生数は、世帯当たり4.3人であったが、平成1年(1989年)には平均1.5人まで減少している。
相続する遺産の平均額は2000万円~3000万円といわれているが、仮に3000万円を4人で分けるのと、1人で受け継ぐのでは、金額的に大きな差があることは明白だ。
■相続財産の重要性
親の金をあてにするか、自助努力で成功するかの考え方は人それぞれだが、低成長・少子化の現在、相続財産の重要性が過去に類を見ないほど高まっていることがお分かりいただけただろうか。
では、どのように次世代へ承継するべきか。
■経済成長率と資本収益率
近い将来、経済成長率9%の時代が再び訪れるかもしれない(可能性は低いと思われる)し、0.5~1%の時代が長く続くかもしれない。
過去100年のグローバル経済成長率は1.6%。先のことは分からないが、この平均成長率1.6%に対し、資本収益率は4~5%で推移している。
資本収益率とは、投下した資本に対してどれだけの利益を生んだかという指数であり、資本に対する収益性を表す指標のこと。資本に対する利益とは、不動産の家賃収入、株式の配当や売却益、債券の利息等があげられる。
時代によって当然差異があるが、過去100年を平均すると、資本収益率が経済成長率を大きく上回っている(このことが格差社会形成の大きな原因といわれている)。
したがって、財産を築くためには、先代から受け継いだ遺産を単に消費するだけではなく、資本として蓄えることが重要と考えられる。
このことは、受け継ぐ側の意識に左右されることが大きい。
相続財産は、棚ぼた、あぶく銭という概念は捨てるべき。お金の価値としては、懸命に働いて稼いだものと何ら変わりない。
■高齢化問題
また、高齢化の問題も次世代への承継を難しくしている。
人生100年時代、60歳から後40年間もお金の心配をしなければならない。
死がいつ訪れるかは分からないので、将来への備えとして、できるだけ蓄えようとするのは当然のこと(長生きリスク、認知症リスク)。
このことによって、死ぬ瞬間が「人生で一番金持ち」ということも多くなっている。
50年前、平均寿命が60歳代後半だったころは、相続人の年齢も30~40歳代がほとんど。いわゆる子育て世代、人生で一番支出が増える時期と重なっており、ある意味、バランスが取れていた時期であった。
現在の相続人の平均年齢は、50~60歳。中には、被相続人が90歳代の場合、相続人が70歳代という事例もよく見受けられる。
これでは、老後資金から別の老後資金へ移転しているに過ぎない。
この傾向が続けば、人生で一番支出が多く、お金を必要とする「子育て世代」へは、財産が承継されないサイクルが確立されることになるだろう。
■次世代への承継
次世代への承継「相続」を成功させるには、まず、世代間で相続の重要性を共有することから始まる。
簡単なことではないかもしれないが、子供にお金で苦労してもらいたいと思う親はいないはずだ。
このギャップを乗り越えない限り、先へ進むのは難しい。
また、相続=死というイメージが強すぎて、家族間で話題にするのも憚られるテーマであることは間違いない。
しかし、相続という言葉の本来の意味は、仏教用語で「連続して絶えないこと」要するに「引き継ぐこと」を意味する。
この言葉のとおり、相続に対して、もっと前向きに考えるべきではないかと思う。
次世代への承継と老後の安心を両立させる方法は必ず見つかるはずだ。
遺言書の作成、家族信託契約、生前贈与等の方法からそれぞれの家族に合ったものを選ぶことが大切。
準備に取り掛かる時期は、早いほどいい。遅くなればなるほど選択肢は、狭まってしまう。
一人一人が相続に対し、積極的に取り組むことによって、家族の幸せ、ひいては、日本の活力回復にもつながると思う。
2021年12月
司法書士 日永田一憲
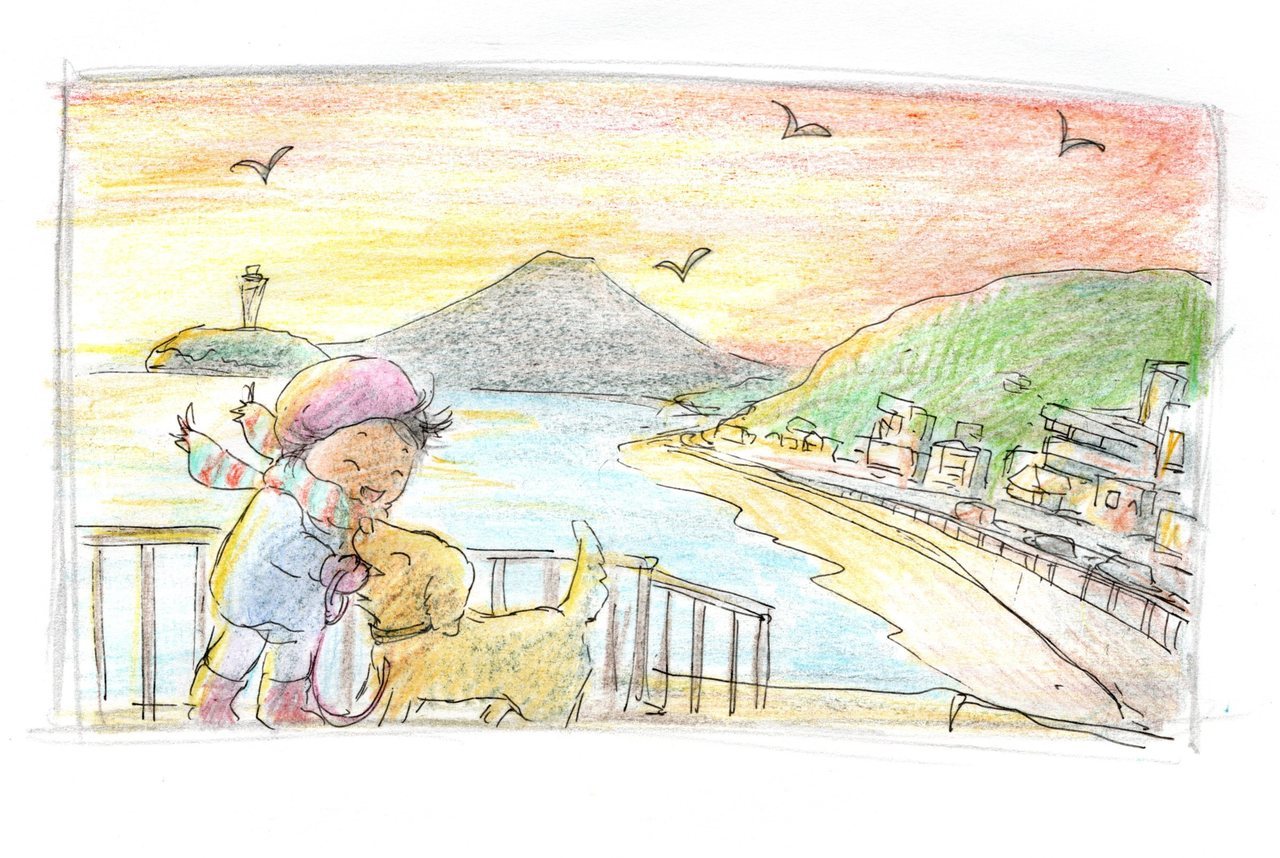
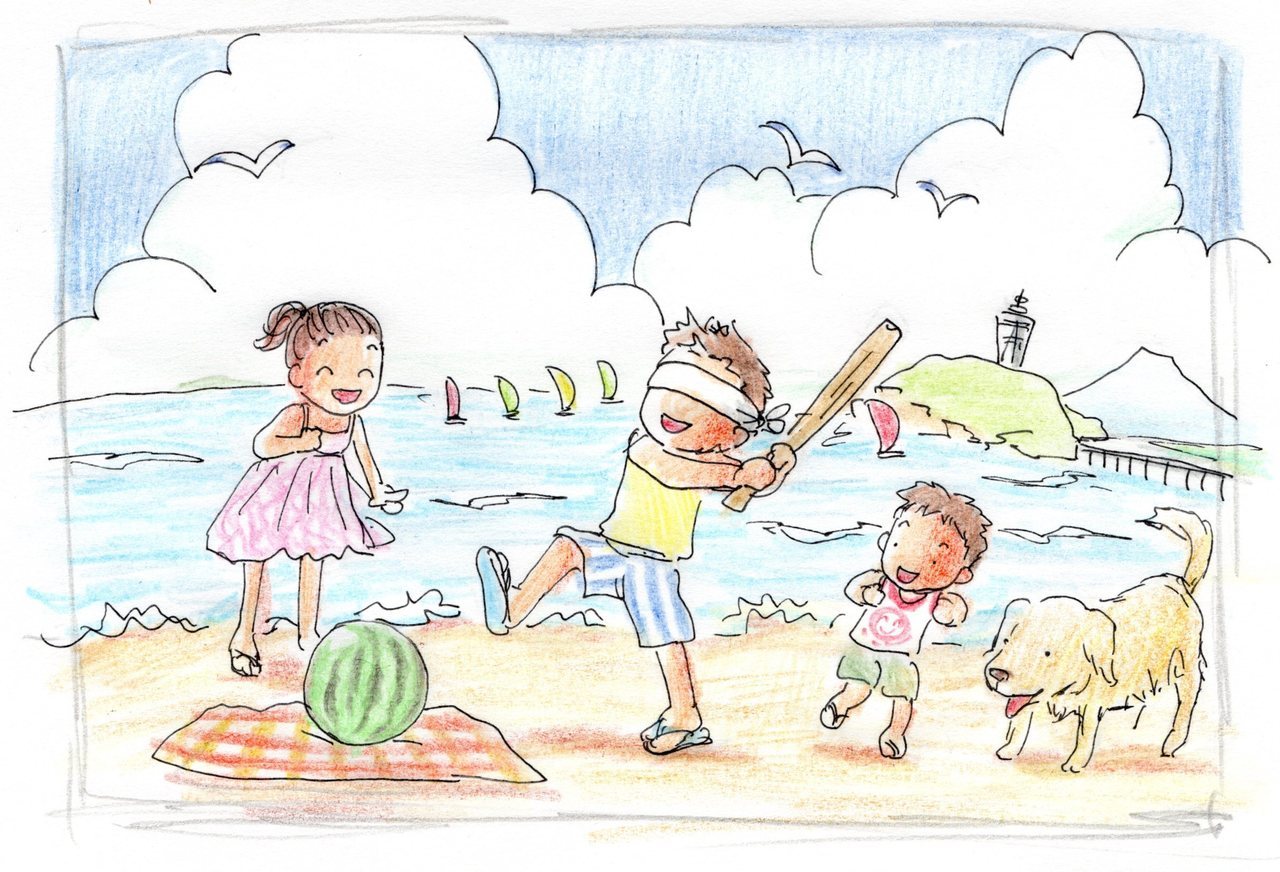
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



