
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
かもめの相続コラム:鎌倉時代の相続制度
鎌倉時代の相続制度

写真提供:鎌倉市観光協会
【家督相続】
戦前の民法では、家督相続という制度があり、生前に家長たる地位、財産とも特定の相続人に譲ることができました。
その家督相続の制度で相続権があるのは、原則として嫡子のみ。ほかの相続人は何も相続できません。
今からすると、違和感のある制度ですが、約70年前までは当たり前でした。
この家督相続の制度は、だいたい室町時代から確立されたといわれ、その後も続き、江戸時代を経て、明治になって新しく民法ができたときも継承されました。
【分割相続】
室町時代の前の鎌倉時代は「分割相続」が主流でした。
嫡子だけだはなく、庶子にも相続する権利(またはその期待権)があり、親の遺産をめぐる争いが幕府の裁判記録にも多数残されています(当時の言葉では、遺跡相論という)。
なぜ、この時代は分割相続の制度が主流だったかというと、12世紀は農業技術が著しく発展したことにより、武士(在地地主)による大規模な開墾がすすめられ、農地が飛躍的に増えました。広大な土地を開発するには、一人の子に譲るよりも多くの子に分け与えたほうが合理的であった、という時代背景が大きな要因です。
【譲状の存在】
当時の領地のある武士は、必ずと言っていいほど「譲状」という書面を遺す習慣がありました。
この土地はだれに、その土地はだれに・・と、自分の財産の譲り先を指定する、まさに現代の「遺言書」のような役割です。
譲り状を書かなかった場合を「未処分」といい一族で穏便に配分できないときは、幕府が配分する(現代の遺産分割調停に似ています)、という規定があったくらいですから、当然に書き遺すべきものだったのでしょう。
【単独相続へ】
しかし、鎌倉時代も後半に入ると、当時の技術水準で開発可能な土地は開発しつくされ、限られた所領の相続をめぐり、相続人間の争いが頻発するようになりました。
もはや、所領規模を適正に維持するためには、分割相続はふさわしくなく、南北朝、室町時代には、嫡子のみがその家長の地位と財産を相続する「単独相続」の制度が確立されていきました。
単独相続の制度は、武家社会とともに江戸時代に引き継がれ、昭和の敗戦まで長く続くことになります。
2019年6月
司法書士 日永田一憲
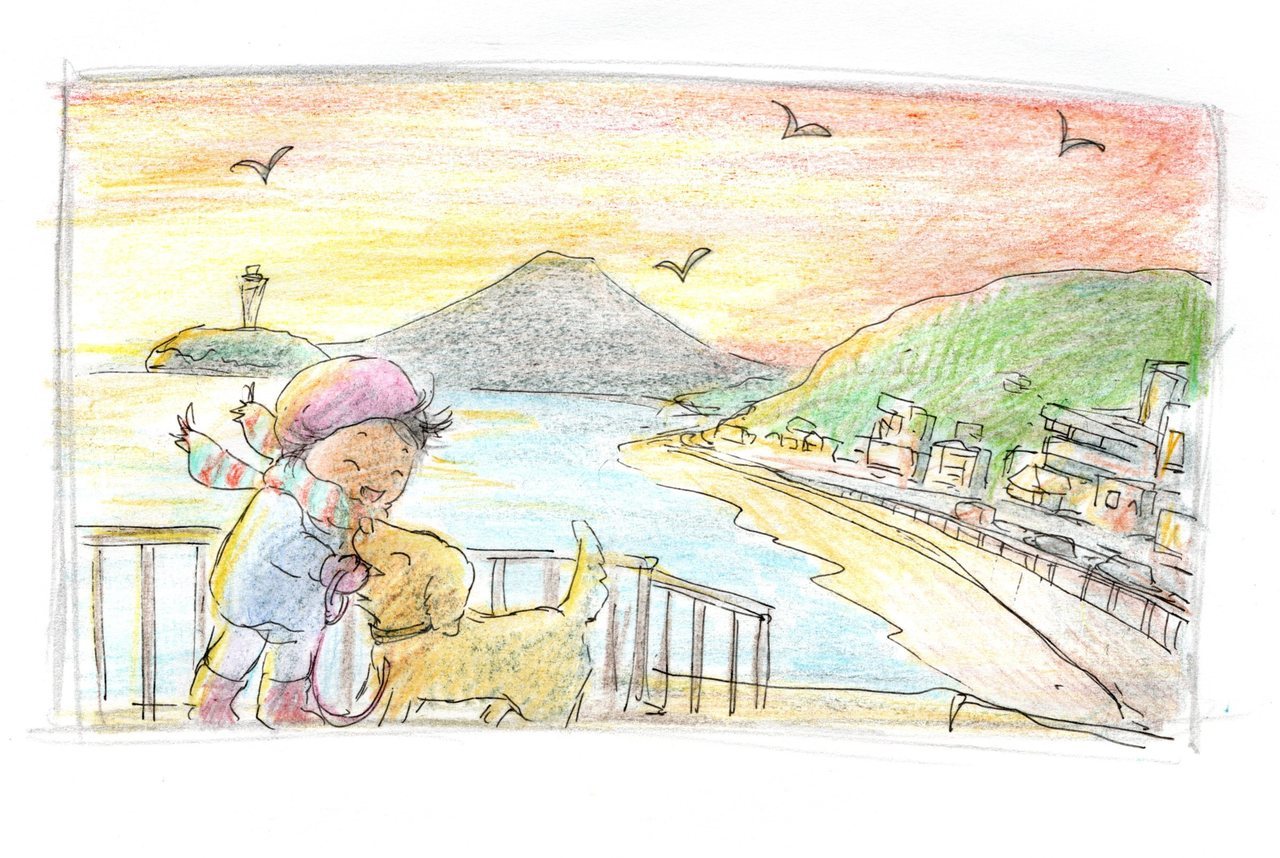
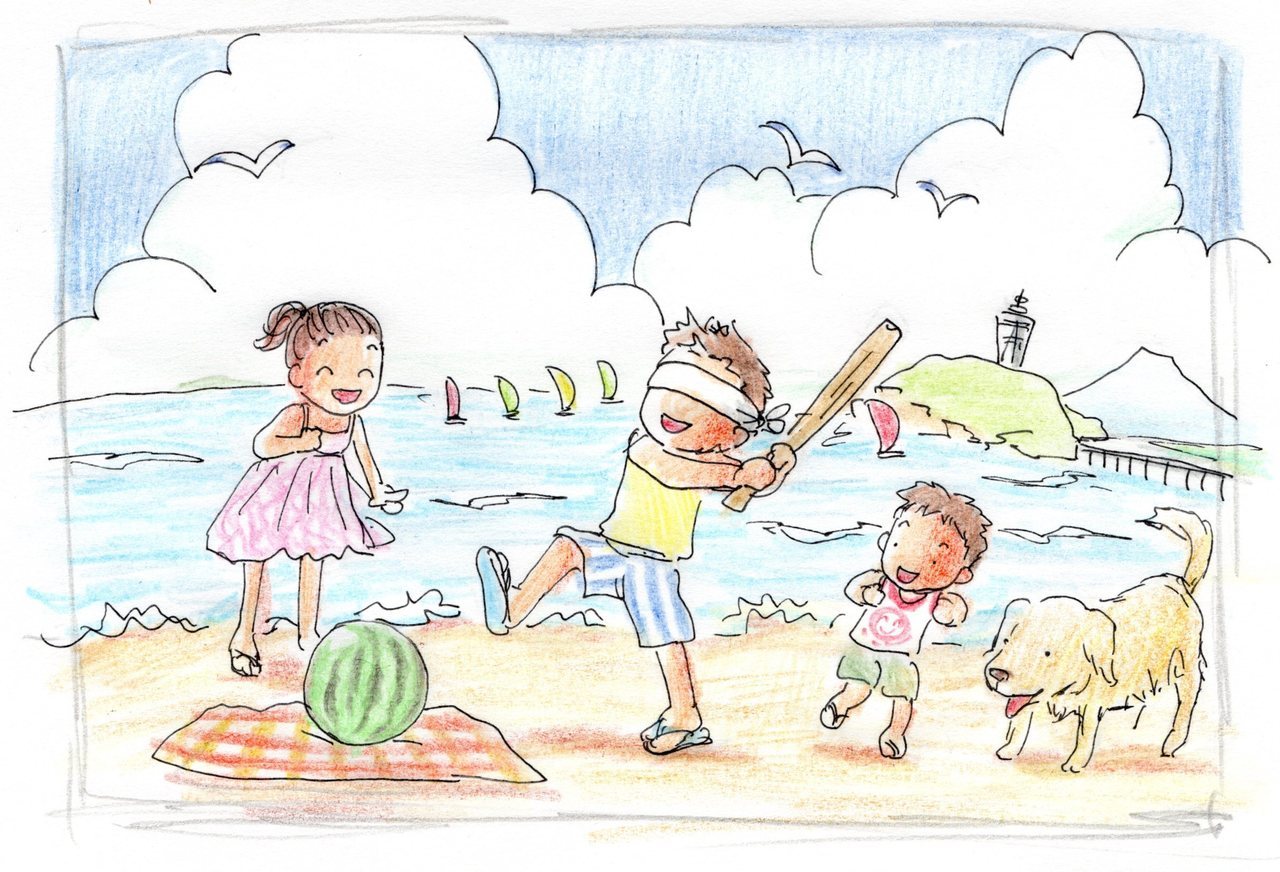
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



