
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
ご相談対応時間:10時~17時半
(事前予約で20時までOKです)
かもめの相続コラム:民法・相続法改正2019|配偶者居住権
民法・相続法改正|配偶者の居住権の強化

2018年7月6日に成立した民法・相続法の改正法が、2018年7月13日に公布されました。今回の改正の内容は、
- 配偶者の居住の権利の強化
- 遺産分割に関する見直し
- 遺言制度に関する見直し
- 遺留分制度に関する見直し
など多岐に渡ります。今回は、配偶者の居住権について説明いたします。
相続を機に「配偶者の居住権(住む家がなくなる)」が問題になることは、私も実務で何度か経験しています。
例えば、子どものいない夫婦で、
- 被相続人(亡くなった方)がA
- 相続人は、配偶者BとAの兄弟XYの合計3名
死亡したA名義の建物に、Bが居住しているというケース。
※子どもがいない夫婦の場合は、配偶者のほか、兄弟姉妹(甥姪)が相続人となります
Aが死亡した場合、残されたBは、引き続き死亡したAと暮らしていた自宅に居住することを希望することがほとんどでしょう。
特にご高齢の夫婦の場合、心身及び金銭的にもBが住環境を変えることは難しくなる傾向にあります。
現行法では、自宅が死亡したAの所有であった場合、Bは自宅不動産の所有権を取得しない限り、その居住権は不安定なものとなります。
他の相続人XY等、B以外の者が当該居住建物の所有権又は共有持分を取得した場合には、Bに賃料の支払義務が発生することや、極端な場合、居住建物から退去する必要性が出てくる可能性があります。
また、他の相続人との話し合いにより、Bが自宅不動産の所有権を取得できたとしても、遺産のほとんどがその不動産だった場合は、金融資産が取得できず、相続開始後の生活費に困るという状態も生じます。
そこで改正案では、Aの死亡から遺産分割協議成立までの短期的な居住権を保護する制度(配偶者短期居住権)と、遺産分割協議成立からB死亡までの長期的な居住権を保護する制度(配偶者居住権)を創設し、配偶者の居住権の保護の強化を図っています。
<配偶者短期居住権>【改正案 第1037条】
配偶者は、被相続人の財産に属した自宅不動産に相続開始の時に居住していた場合には、その不動産の取得者に対し、一定期間、自宅を無償で使用する権利が認められます。
一定期間とは、相続開始から遺産分割終了まで又は相続開始から6カ月を経過するまで認められます。遺贈等により、第三者が自宅不動産の所有権を取得した場合は、その第三者から消滅請求がされてから6カ月を経過するまでは存続します。
<配偶者居住権>【改正案 第1028条】
配偶者は、被相続人の財産に属した自宅不動産に相続開始の時に居住していた場合において、一定の要件に該当するときは、その居住していた建物について「配偶者居住権」を取得できます。
一定の要件とは、
- 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき
- 配偶者居住権が遺贈又は死因贈与の目的とされたとき
存続期間は原則として終身となり、対抗要件として、配偶者居住権設定の登記が必要となります。
また、配偶者居住権は、持ち戻し免除の規定(遺産全体から除いて計算する)が推定されることにより、遺産分割の際に配偶者はより多くの財産を取得できるようになります。
以上のように、配偶者居住権は、相続開始後の配偶者の保護を図るために創設された画期的な制度です。
※施行は公布日から2年以内とされています
2018年9月
司法書士 日永田一憲
法務省の資料はこちら↓
http://www.moj.go.jp/content/001263482.pdf
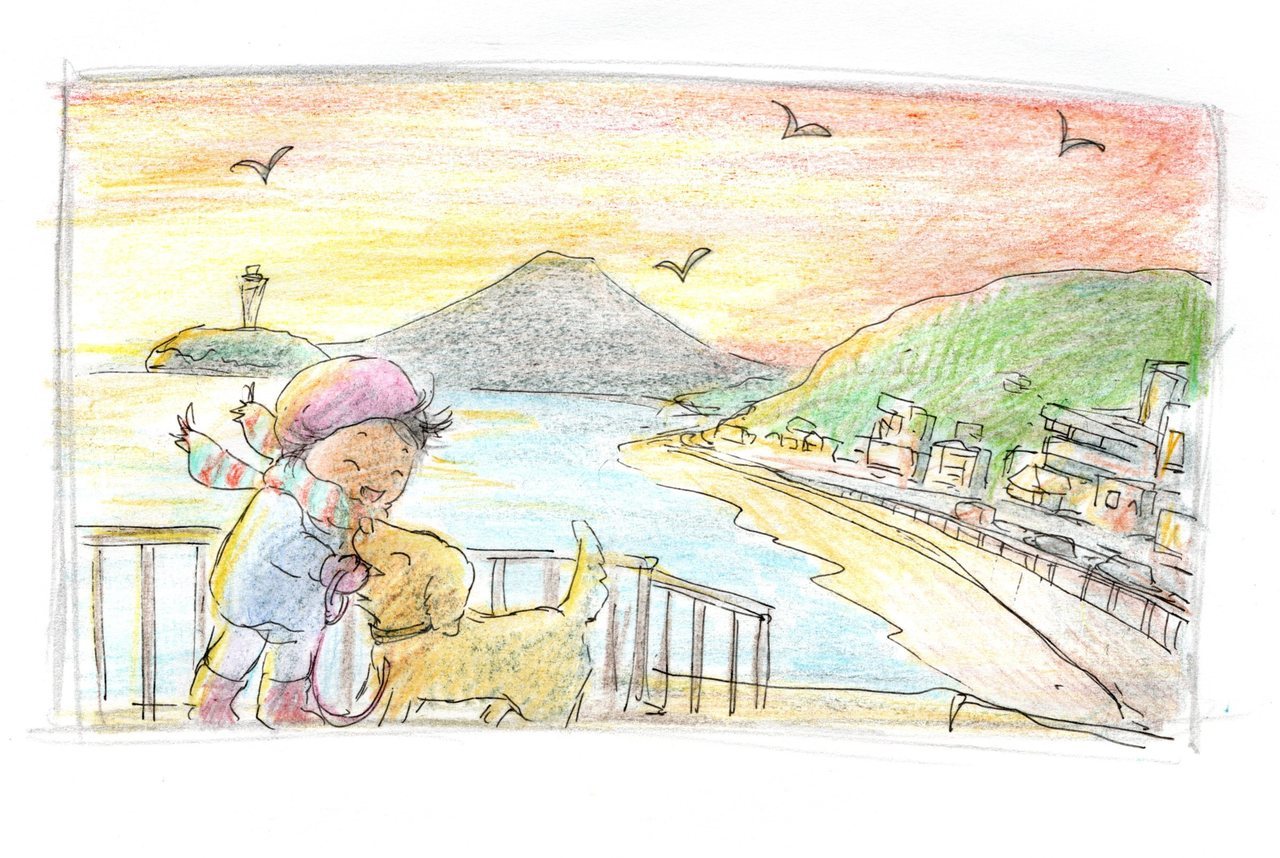
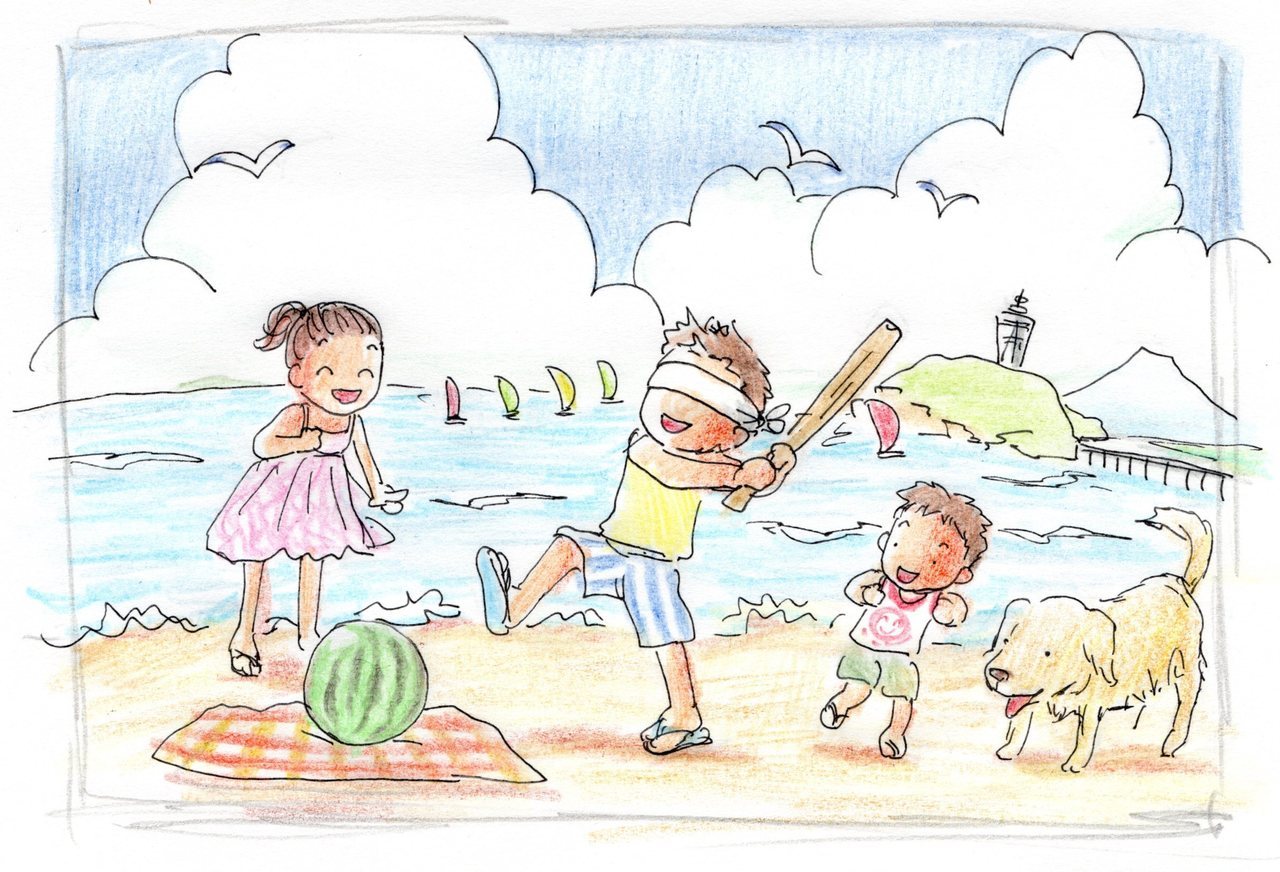
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります
事務所紹介

かもめ総合司法書士事務所
代表者
司法書士・行政書士
日永田一憲(ひえだかずのり)
昭和44年生れ
鎌倉市在住

当事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります



