
鎌倉で相続の相談なら、かもめ総合司法書士事務所
鎌倉・相続相談ひろば
かもめ総合司法書士事務所<鎌倉市由比ガ浜>
かもめの相続コラム:特別の寄与料
特別の寄与料はいくら?

■遺産分割で問題になる寄与料とは
平成30年の民法改正前から、民法には「寄与分」の規定がありました。
ただし、この規定は、被相続人の財産形成や療養看護に特別の寄与をした「相続人」を対象とした制度であり、法律上の相続人ではない近親者は、どんなに貢献していても、寄与として考慮されることはありませんでした。
分かりやすくいうと、相続人の中で、
- 財産形成 被相続人の事業を助け資産を増やした人など
- 療養看護 日常の世話や介護をした人など
が該当します(いずれも無償が要件)。
■相続人以外の「親族」も対象に
法改正により、被相続人の財産形成や療養看護に特別の寄与をした相続人以外の「親族」も相続人に対し、寄与分を請求できるようになりました。請求できる人の幅は広がりましたが、法律上の親族に限られます。
例えば、
- 長男の妻→請求できる
- 従兄弟→請求できる
- 内縁の妻→請求できない
- 同性パートナー→請求できない
となります。
補足ですが、親族とは6親等内血族、配偶者、3親等内の姻族を指します。
■特別寄与料の計算方法
特別寄与料は、相続開始と同時に自動的に決まるわけではなく、相続人に請求する必要があります。
原則として、当事者間の協議で定めますが、協議ができないときは、家庭裁判所に決めてもらうことができます。
よくご相談の際に、寄与料について、
「遺産は○億円あるから、○千万円は認められますかね?」
と聞かれることがありますが、家庭裁判所の計算方法はかなりシビアです。
遺産総額に対する割合ではなく、
「もしヘルパーさんなどの第三者に療養看護を頼んでいたらいくらかかったか」
を基準に支払わなくてもよくなった分(実費)を「寄与分」「特別寄与料」として認めるという方法です。
計算式は、次の通りとなります。
寄与料=ヘルパーさんの日当額×療養看護日数×裁量割合
裁量割合とは、介護等の専門家(プロ)に頼んだ場合よりは費用を控えめに計算するため、5~8割程度を乗じて、寄与料を減額することをいいます。
例えば、長男の妻が、被相続人を1年間にわたり、1日1時間程度介護していたという場合、介護費用を1時間あたり6000円とすると、
6000円×365日×0.7(裁量割合)=153万3000円
と計算され、介護をした長男の妻は、相続人に対し、153万3000円を特別寄与料として請求できるということになります。
遺産の額にもよりますが、1年間献身的に介護してきた特別の寄与料が153万3000円、意外と少ないなあ、と感じられる方も多いのではないでしょうか。
■その他の要件
なお、特別寄与料は、当事者同士の協議には期限はありませんが、家庭裁判所に決めてもらう場合は「相続の開始および相続人を知ったときから6カ月以内」という期限があります。
また、寄与分・特別寄与料として認められるには、通常の扶養の範囲を超える寄与をしたことを証明する必要があり、金額は、遺産総額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできない、という制限もあります(遺贈優先)。
以上のように、何かとハードルが高い寄与分・特別寄与料ですが、世の中の動きとして、相続人以外の寄与を何らかの形で評価しようという動きが高まってきていることは事実です。
家族という概念が変化している現在、改めて検討が必要な課題であると思われます。
2021年3月
司法書士 日永田一憲
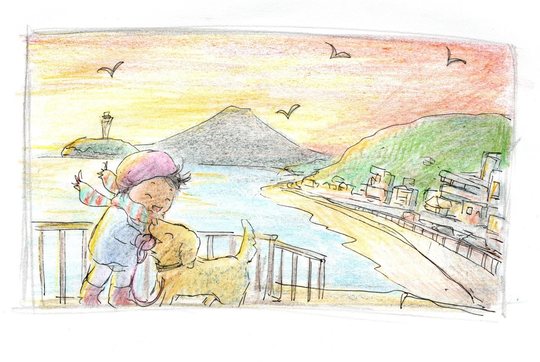
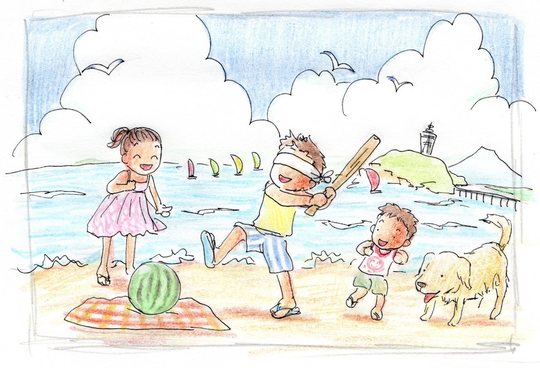
突然の相続で何から手をつけたらよいか分からない、、そんなときは、司法書士の無料相談をご利用ください
神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-9-62フォーラムビル2階、鎌倉駅から0.6キロ、若宮大路沿い
営業時間:平日10時~17時半(事前予約で20時までご相談承ります)
相続や遺言、よくあるご質問
相続や遺言の相談は無料ですか?
初回のご相談は無料で承ります
お気軽にお問い合わせください
見積りをお願いできますか?
報酬及び諸費用について、
事前に料金表をご提示します
相続登記は全国対応ですか?
全国どこの法務局でも登記可能
遠方でもOKです

法律サービスを通し安心と幸せを
かもめ総合司法書士事務所では、相続手続きをスムーズに行うことで、相続人の方のご負担を軽減し、これからのご家族の安心と幸せをサポートすることを使命と考え、日々、業務に取り組んでおります


